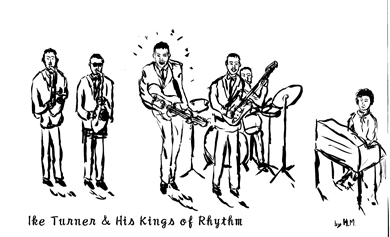
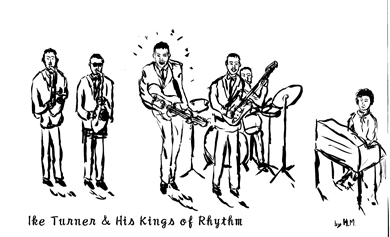
ティナ・ターナーが"Private Dancer"というアルバムで復活した当時アナログ盤を購入した私は結構良く聴いていました。いま思えば80年代のアルバムにありがちなベテラン歌手をブラコン等のはやりの曲に押し込むというやり方とは違って、アル・グリーンの Let's Stay Together やアン・ピーブルズの I Can't Stand The Rain などのソウル時代の曲をカバーしたりしてティナがイカしていた70年頃の雰囲気を大事にするような感じがありました。 その時も後のティナの自伝的映画でもかつての相方のアイク・ターナーに対する一般的な印象は「家庭内暴力夫」というものでした。"Proud Mary : The Best of Ike & Tina Turner"というアイク&ティナ・ターナーがヒットをまとめて出していた60年代初期のスー時代と70年前後のミニット/ユナイテッド・アーティスツ時代の編集盤(60年代中・後期の曲、特にフィル・スペクターがプロデュースした"River Deep, Mountain High"からのタイトル曲が含まれていないのは残念!)には、ティナのハスキーで思いきりのよいシャウトが聴ける曲の数々と脚線美を強調するステージやジャケットの写真があります。歌い上げるティナの横でギターを手にしてティナを見つめるアイク・ターナーの姿に邪推を交えると、「別にこの人がいなくても十分じゃないの?」なんてことを思ったりしますが、果たしてそうでしょうか。
元々はピアニストであるアイク・ターナーはキングス・オヴ・リズムを率いて1951年に Rocket 88 という曲をメンフィスのサンで録音しました。ピアノのイントロと歪んだギターが印象的なこの曲は「最初のロックンロール・ヒット」とも言われています。ところがこの曲はチェスの配給となりボーカルのジャッキー・ブレンストンの名義になってしまいます。当時のサンやモダンといったレーベルでアイクが期待されていた役割はバック・ミュージシャン兼タレント・スカウトでした。"The Sun Sessions"(主にサン時代)に Rocket 88 を含む"Rhythm Rockin' Blues"(主にモダン時代)、"Ike's Instrumentals"(モダン時代とスー時代のインスト集)、"Blues Kingpins"(主にモダン時代)、"King Cobra"(コブラ時代)でアイク・ターナーが参加した他の人の曲やキングス・オヴ・リズムの曲が聴けます。彼自身「ラヴァーボーイ」名義で曲を出していますがボーカルはイマイチで、本人作曲の曲もスペシャルティのギター・スリムやパーシー・メイフィールド、ロイド・プライスなどから「影響を受けた」ものといった具合です。とはいえアイクの一番の売りはストラトキャスターの「ワミー・バー」(要はトレモロ・アーム)を駆使して軽快で時にはブルージーなフレーズやリフを聞かせることでしょう。最初の妻のボニー・ターナーやビリー・ゲイル(ズ)、デニス・バインダー、ビリー・"ザ・キッド"・エマーソンといった人たちのバックでピアノのシャッフルの初期のR&Bからギターを弾きまくりのハードなブルースからスローなものまで、幅の広い曲調です。キングス・オヴ・リズムではトミー・ホッジという野太い声のボーカルの (I Know) You Don't Love Me [Get It Over Baby] や Matchbox [I'm Gonna Forget About You] に Down and Out [How Long Will It Last] はアイクのギターとの相性が良くなかなか素晴らしいです。インストの曲では All The Blues All The Time というブルースの名曲のメドレーでアイクがギターをそれぞれの曲のスタイルをまねて演奏しているのが聞き物です。こういう演奏面でなかなかのモノがあるアイク・ターナーに足りないものは、ヒットを生み出せるオリジナルの曲と歌手でした。
アイク&ティナ・ターナーでの A Fool in Love や It's Gonna Work Out Fine や River Deep, Mountain High、Proud Mary といったヒット曲ではティナの方に注目が行きがちですが、"Bold Soul Sister"という60年代末頃のブルー・サム時代の編集盤にはブルースのカバーが収録されていて、3 O'clock in the Morning Blues や I Smell Trouble、Dust My Bloom では、ティナに負けじとアイクのギターが泣きまくりです。ティナの激しく未来へと突き進もうとする前向きさとアイクの昔に引き戻そうとする後向きさとのせめぎ合いが感じられます。どさ回りのチトリン・サーキットから華やかなコンサートへと舞台がかわる中で元々が気質が違う二人が袂を分かつのが必然だとしても、フィル・スペクターなどの外部の人にはうかがい知れないノリが二人にはあったのでしょう。(2005.02.25)(2006.11.20)