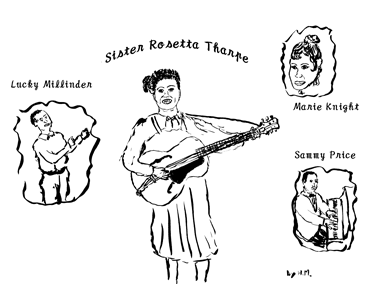
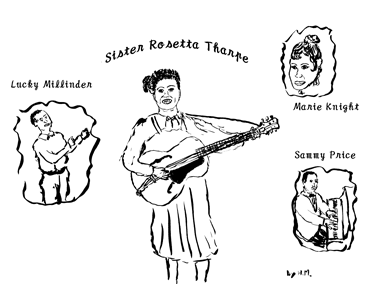
20世紀の始め頃から主に黒人のバプティスト系の教会によって、声の表現に柔軟性を持たせたり楽器を導入してリズムをつけたり女性を聖歌隊に混ぜたりと、現在の躍動感と高揚感溢れる音楽へとゴスペルは発展してきたそうです。楽器やコーラスがつく音楽は勿論他にもあって、ゴスペルと世俗音楽との区別がきつい時代には歌う内容が信仰についてなのかどうかだけでなく、楽器の演奏法やコーラスのアレンジでも区別をつけていく感じでした。結局は50年代に世俗音楽のレイ・チャールズがゴスペルの手法を取り入れたり、ゴスペルのサム・クックがより多くの聴衆を求めて世俗音楽に転ずるような動きが出てきて、それに対する批判も押しながすような大きな流れがゴスペルと世俗音楽との間に生じます。そのソウルを生んだ先駆者より前の40年代にゴスペル歌手でありながらジャズやブルースといった世俗音楽のスタイルも取り入れた人がいました。シスター・ロゼッタ・サープはビブラートの効いた低めのメゾソプラノの声を朗らかに伸ばすだけでなく、フォーク・ブルースのギターも軽快に速弾きするなかなかかっこいい人であります。教会の感情の込められた声の掛け合いは40年代ではまだ世俗音楽に取り入れられていなくて、ギターを弾くソロ歌手だった彼女の語り口とノリは陽気で洗練されたスイング・ジャズのそれです。ゴスペルの全貌が一般にも明らかになる前の時代に、彼女は都会の白人に受け入れられるようなゴスペルの明るい側面を発揮していました。
マーティン・スコセッシ監督の制作総指揮によるブルースを題材にしたTV映画のサントラ盤である "A Musical Journey" には、数少ない戦前の女性のギター弾きの曲も取り上げられています。既に30年代にレコードを出しているメンフィス・ミニーは Me and My Chauffeur Blues で腸に来るようなシカゴ・ブルースを聞かせます。シスター・ロゼッタ・サープの44年の Strange Things Happening Every Day でのギターはチャック・ベリーの軽快なロックンロールのようです。この曲で共演しているサミー・プライスの転がるようなブギウギのピアノは、後に出た一般にロックンロールの元祖と言われるビッグ・ジョー・ターナーの Shake, Rattle & Roll のピアノを思わせるものです。音の選び方や細かい技法にはブルースの雰囲気がありますが、メンフィス・ミニーのように明らかにブルースという曲ではありません。厳格なマヘリア・ジャクソンにしてみればジャズも「邪悪な音楽」ということになりますが、教会にとって越えてはいけない最後の一線の先にブルースがあったようです。
38年から40年代にかけてのデッカ録音の曲のベスト "The Gospel of the Blues" や4枚組の "The Original Sister" では、時代を追うごとに彼女の音楽的な変化が聞き取れます。My Man and I や This Train や That's All や Sit Down の素朴なギターの弾き語りから始まり、Rock Me や Shout, Sister, Shout や I Want a Tall Skinny Papa でのラッキー・ミリンダーのビッグ・バンドとのスイング・ジャズ、Vディスクなどの第二次世界大戦中の軍の慰問の為の録音、Singing in My Soul や Strange Things Happening Everyday や Jonah でのサミー・プライス・トリオとの軽快なジャズ、そして Didn't It Rain や Up Above My Head I Hear Music in the Air や My Journey to the Sky でのアルトのマダム・マリー・ナイトとの小粋なデュエットといった具合です。伝道師としてあちこちの教会を回ってライブをする一方、白人の聴衆のいるコットン・クラブでキャブ・キャロウェイのビッグ・バンドと共演したり、ミリンダーと組んでノベルティを歌ったりしていた彼女ですが、その後の50年代はじめにマリー・ナイトとブルースを歌ったことでゴスペル純粋主義者の猛烈な怒りを買ってしまいます。それが原因でマリー・ナイトはブルースに転じ、ロゼッタ・サープはほとぼりが冷めるまでヨーロッパでツアーをしたりする羽目になってしまいます。彼女達がどういうブルースを歌ったのかは私は分かりませんが、歌う内容がゴスペルとブルースとでは明らかに違うだろうし、その上マッカーシーの赤狩りに代表される保守的な締め付けがきつかった時代がその背景にあるのでしょう。それでも彼女の曲を聞いていたら「何で今さら野暮なことを言い出すの?」というくらい、既に音楽的にはゴスペルと世俗音楽との壁は大きく崩れていたように思います。ちなみにマリー・ナイトは60年代半ばにミュージコーというレーベルからジュリー・ロンドンで有名な Cry Me a River の素晴らしいカバー("Bluesoul Belles volume 4" に収録されています)を歌っています。 このようなR&Bの曲などを出した後はゴスペルに戻って、80歳を過ぎた現在でもなかなか渋い新譜を出しています(こう書いた後、2009年の秋に亡くなりました。ご冥福をお祈りします)。
デッカ以降のサープの作品では、マーキュリーでの56年の "Gospel Train" があります。既にバック・ビートの効いたR&Bの時代で、レイ・チャールズ風のブルージーなものからドゥー・ワップ、チャック・ベリー風のロックンロール調まで様々です。彼女のギターは控えめですが歌声はまだまだ張りがあります。ライナー・ノーツでは「これまで未発表のヨーロッパでのライブ」としか記されていない "Live in 1960" では、彼女の歌声とエレキ・ギターだけの簡素な曲が聞けます。Vacation in the Sky や Can't No Grave Hold My Body Down などでは、曲の前の説教師風の語りが彼女の教会でのライブを思わせます。いつもの陽気な曲だけでなく、Two Little Fishes, Five Loaves of Bread やThe Gospel Train などはスローなブルースのノリも感じられます。彼女のよく伸びて震える声が際立って聞こえます。権利的にちょっと曰く付きのイタリアの編集盤"From Gospel to Blues" には、60年前後のゴスペルコーラスがついて彼女のギターが聞かれない曲や60年代後半以降のオルガンが印象的なステレオ録音の曲も収録されています。晩年に近付くと彼女の声も低くなり衰えも感じますが、レイ・チャールズ以降のソウルで知られるようになった教会のゴスペルのノリが彼女の歌に現れてきます。全盛期以降はレーベルを転々としているためにまとまった編集盤がない人なのですが、そういう曲も腰を据えて聴いてみたい気にさせる人です。(2006.05.29)(2009.08.01)(2009.12.29)