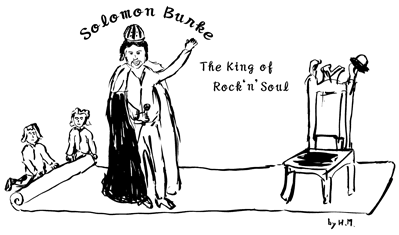
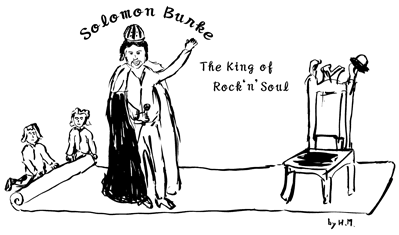
教会での牧師の説教を耳にしたことがあるでしょうか?厳粛なカトリックはともかくバプティストの牧師の説教の語り口は非常に音楽的です。マーティン・ルーサー・キング牧師の声が割かし有名だと思うのですが、彼の演説を要約した"In Search of Freedom"というCDの中の I Have a Dream の件なんかはまるで韻を踏んだ歌のようです。"Legendary Sermons"などで聞けるアレサ・フランクリンの父であるC・L・フランクリン牧師の説教は音楽的な声の響きに素晴らしいものがあります。張りがありよく通る男らしい声で言葉を印象的に簡潔に区切り、聴衆は「そうだ」などなど合いの手を入れ、最後には牧師は一言一言を叫ぶように歌い上げます。ゼーゼーするような息継ぎの音をマイクに生々しく乗せるのがちょうどリズムを取る効果を生んでいて、その盛り上げ方は聴衆を煽動しているかのようです。日本のお坊さんの法話や落語家の人情話には牧師の説教と内容が共通するものがあるかも知れませんが、語りからそのまま歌い出すような音楽的なノリはありません。日本では考えられない程宗教と音楽とのつながりが深いアメリカでは、ゴスペル歌手の中から世俗の歌手になる人が出てくるのは必然とも言えます。ソロモン・バークは10代になる前から「驚異の少年説教師」としてフィラデルフィアの自分の家族の教会で説教を始め、ゴスペルのラジオ番組を自分で持っていたそうです。彼の説教がどういう内容だったかはわかりませんが、北部出身でありながら南部のソウルの熱さを持った歌声からしたらC・L・フランクリンのような人を鼓舞するものだったのでしょう。
ソロモンにとって最初の世俗音楽の録音は、50年代半ばのアポロ・レコードでのものです。"This is It" というこの時代の編集盤の曲を聴くと、ゴスペル色が出ているのは彼の祖母に捧げる形になった Christmas Presents くらいで、ボクシングのヘビー級チャンピオンのジョー・ルイスにちなんだ You Can Run But You Can't Hide など、ロイ・ハミルトンやアイヴォリー・ジョー・ハンターのような声の響きにゴスペルの影響がかすかにあるバラードものが殆どです。とはいえ、この時代で既に高音と低音を自在に行き来するしなやかな歌声が聞けます。
"Atlantic Rhythm & Blues 1947-1974"ではじめてソロモン・バークを知り、そして 彼のアトランティック時代の二枚組の編集盤である"Home in Your Heart"の一枚目から改めて彼の曲を聴いてみると、60年代後半にソウルが一般的に売れるようになる一歩手前に彼がいたという印象があります。初期の甘い歌い方の Just Out of Reach (of My Two Open Arms) はカントリーを歌って成功したレイ・チャールズを意識していていますが、その後の全盛期はバート・バーンズのプロデュースによる合唱隊とラテン的な要素もあるリズムを強調したアトランティック流のロックン・ソウルをバックに、ソロモン・バークはメロディに言葉を乗せる説教師風の歌い方で聴く人を高揚させます。Words、If You Need Me、The Price、Got to Get You off My Mind、Home in Your Heart のバラードからアップ・テンポまでの歌いこなしや説教節もそうですが作曲陣も聞き逃せません。 I'm Hanging up My Heart for You、Tonight's the Night のドン・コヴェイに加えて、Down in The Valley、Cry to Me、Goodbye Baby (Baby Goodbye)、映画の「ブルース・ブラザーズ」でもカバーされている Everybody Needs Somebody to Love のバート・バーンズ(ラッセル)の曲を聴くと、ブルージーでかつ教会の熱気のあるニューヨークのソウルの神髄に触れるようです。
"Home in Your Heart"の二枚目はアトランティックが南部のメンフィスの本場の音を求めた時期の曲が多く、Take Me (Just As I Am) や I Wish I Knew を始めカントリーの影響もあるゆったりしつつ締まった南部のソウルに乗ってなかなかの語りと歌を聴かせてくれるのですが、どうも全盛期に比べるとさっぱりしておとなしい感じがします。同じアトランティックのアレサ・フランクリンやウィルソン・ピケットは南部の音を得て時流にも乗って白人にも広く聴かれるような成功を収めたのと対照的です。ソロモン・バークのスタイルは教会の音と深く結びついていた泥臭いもので、南部の黒人や本場志向のファンに受けは良かったはずですが一般受けがあまり良くなかったのかもしれません。ただ、この時代のアルバム "King Solomon" と "I Wish I Knew" 全体を通して聴くと、諭すような説教節や Keep a Light in the Window のようなドスの効いた迫力ある歌い方は、決して全盛期に劣りません。
アトランティックを去った後はまずベルというレーベルでCCRの Proud Mary を説教風の語りを入れて素晴らしい解釈で聞かせてくれます。この曲をはじめとしたマッスル・ショールズ録音の "Proud Mary" には、レイ・チャールズの泣きの解釈とは異なる That Lucky Old Sun のようなカバー曲が、南部ソウルの醍醐味十分に堪能できます。これらの充実した作品の後はレーベルを転々としていて、ポップ・ソウルなMGM録音の "That's Heavy Baby" や凡庸なディスコのチェス録音の "The Chess Collection" でも時々聞けるゴスペル・ソウルはやはり素晴らしいです。知る人ぞ知るスワンプ・ドッグのプロデュース曲の編集盤 "Let Your Love Flow" では、Please Don't Say Goodbye to Me のようなディスコの音にソウルフルな歌声や説教節を乗せている一方で、Sidewalks, Fences and Walls のような佳作のバラードもあります。80年代にはニュー・オーリンズのラウンダーというレーベルから、割とブラコンの音作りの "A Change is Gonna Come" や、簡素なバックながらも全盛期の迫力そのままで自身のヒット曲を歌う "Soul Alive!" が出たりしています。90年代にはニュー・オーリンズのブラック・トップから、昔のギター・ブルースやジャズ・ブルースを歌った "Soul of the Blues" や、ビッグ・バンドを従えた王様さながらの " Live at House of Blues" など、なかなかの作品を出しています。
21世紀になった今でもソロモン・バークは歌手稼業の傍ら教会を主宰し、葬儀屋も経営するなど精力的な人生を送っています。マルマルとして貫禄のある彼の姿を見ると聖職と世俗との狭間で矛盾に悩む暇なんか無さそうに見えます。「ロックとソウルの王様」の戴冠式よろしく王冠とマントを身にまとい歌う彼のライブは中々面白かったようで、"Soul Alive!"や " Live at House of Blues"などのライブ盤ではそんな彼の姿が思い浮かぶようです。彼の円熟した歌声とジョー・ヘンリーによる簡素でブルージーで気を配った音のおかげで、ただ昔の栄光を追い掛ける感じでない今を捕らえているファット・ポザムというレーベルから出た "Don't Give up on Me" は素晴らしい出来です。若い頃の説教風の歌い方になかったタイトル曲の切ない歌い方に加えて、ヴァン・モリソンにトム・ウェイツ、エルヴィス・コステロの曲など渋さの極みの選曲がたまりません。ニック・ロウの提供した The Other Side of the Coin はソロモン・バークの神に仕える身でありながら世俗のソウル歌手であることの葛藤についての曲だそうですが、「そう言われれば俺ってそうかもな」と流せるしたたかさがソウルなのだと私は思います。この後もシャウトというレーベルで、ドン・ウォズのプロデュースした "Make Do with What You Got" や、カントリーやルーツ・ロックの女性歌手とも共演している "Nashville"、エリック・クラプトンが作曲に参加したりアコースティック・ギターが目立つ "Like a Fire" を出して、円熟した歌声を聴かせてくれます。ピーター・ギュラルニックの本「スウィート・ソウル・ミュージック」に出てくるソロモン・バークについての記述は、ソロモン自身の話も含めてとても魅力的です。誠実と狡猾、真面目と冗談、聖と俗を歌声さながらに行き来するこの人物の話は、単なる歌手の成功物語が薄っぺらに感じるほどです。あの大きな腹に詰まっているエネルギーに触れた人は、ご利益があったかはともかく面白い場面に出くわしたことでしょう。
既にご存知の方も多いと思われますが、2010年の10月10日に亡くなりました。ご冥福をお祈りします。生前に彼が出した最後のアルバムとなってしまった "Nothing's Impossible" は、同じく今年亡くなったウィリー・ミッチェルがプロデュースしたもので、アル・グリーンのハイ・サウンドとソロモンの歌声の組み合わせがとっておきの贈り物になっています。この前初来日したばかりだというのに、ただただ驚きただただ残念です。(2005.10.23)(2009.03.11)(2010.10.13)