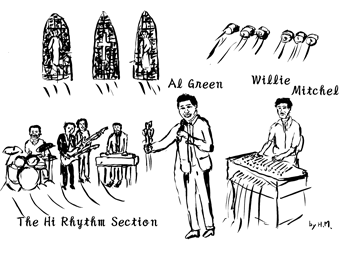
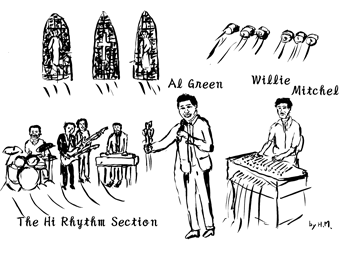
アル・グリーンのことを私が知ったのは、ティナ・ターナーがカバーした Let's Stay Together でした。ティナのバージョンは情熱的に声を震わせるところからサビの爆発させるような歌い方が、当時アメリカのヒットチャートのミーハーだった私からしてもとても魅力的なものでした。その後本家のアル・グリーンの曲を聴きました。ソフトで囁く歌いまわしとサビのファルセットの切ない感じがこれまた良いのですが、曲の構成がポップでシンプルなせいかあっという間に過ぎていくような感じでした。まあ、80年代の4、5分の曲のコッテリしたアレンジに比べたら、70年代初期の3分前後の曲は塩分控えめの淡い味でしょう。そんな中でアルのハイ時代の"Greatest Hits"を図書館で借りて聴いたのですが、これにはホントにはまりました。ホーン、ストリングス、リズム隊などから繰り出される音数が少なくてスローでタイトなノリが適度な緊張感と心地よさをもたらし、アル・グリーンのリズムへの乗りかかり方はまさにゴスペルのもので、やわらかい綿菓子に包んだ歌声からは時々ゴスペルの力強さが垣間見えます。Tired of Being Alone、Call Me、I'm Still in Love with You、Here I Am、Love and Happiness、You Ought to Be with Me、Look What You Done for Me、Sha La La、L-O-V-E などなど、Let's Stay Together で感じた物足りなさが吹き飛ぶような曲が立続けに耳に入っていきます。このメロディがブルースとジャズとポップの間を浮遊する感覚はこの時期のアル・グリーンでしか味わえないもので、はじめて聴いた時は勿論、今聴いてもゾクゾクします。"Greatest Hits"を自ら手に入れた後はそれに満足しきってしまい、アルの他のアルバムを聴いてみようとは時々思ったもののそのままでした。
"I Can't Stop"という新しいアルバムがブルー・ノート(このごろジャズに留まらず、ノラ・ジョーンズなどのアルバムを出しています)から出て、ラジオで1、2曲聴いたところアルが全盛期だったハイ時代の音そのままといった内容で、「今さらなんだかなあ」と思いつつ購入してみました。必ずしもハイ・サウンドの甘さに徹した内容ではなくて、I've Been Thinkin' 'Bout You などファンキーでツボにはまる曲もあります。ライナー・ノーツには彼の数々の名曲に携わったプロデューサーのウィリー・ミッチェルとアルの二人並んだ写真があり、お互い歳をとったもののやってることは昔と変わらないといった様子が写っています。元恋人にグリッツ(アメリカ南部のソウル・フードの鍋物)をかけられて大火傷を負わされてその場で元恋人は拳銃自殺したなんて事件があってから、アルは教会を手に入れて自ら牧師になりついには世俗音楽からも離れたという風に私は覚えていたので、ハイ時代と現在の間に何があったのかを彼のアルバムで追うことにしました。
"Testify"という80年代後半のA&M時代の彼の編集盤にも旧知のウィリー・ミッチェルと組んだ曲が数曲あって、そのハイ・サウンドを意識させる曲調はやっぱりしっくりきます。その他は80年代はやりのピコピコした電気的な音をバックにした曲です。映画「三人のゴースト」で使われていた Put a Little Love in Your Heart はユーリズミックスと組んだ曲で、「ああ、そういえばこの曲は流行っていたっけ」と思い出しました。その当時はヒットチャートへの興味は薄れていたのでちょっと聴いただけでアル・グリーンだとは気付かないでいましたし、なにしろアニー・レノックスの声とアル・グリーンのファルセットが同じような音域で歌うパートが重なりあうので、私個人としては彼の印象がいまいち薄いです。世俗音楽から離れゴスペルのアルバムを出していた時期もあったそうですが、アル・グリーンは結局は牧師を辞めずに世俗音楽もやるというスタイルになっています。サム・クックやレイ・チャールズの時代にあった宗教音楽と世俗音楽との壁がこの時代には大分曖昧になっている感じがします。ゴスペル出身のソウル歌手が成功を納め世間的に認知されるようになって、「その人が自分の長所を活かして社会に有意義なことをする」ことも信仰心の現れとして宗教も容認するようになったということなのでしょうか。キリスト教徒が少なく宗教と音楽とのつながりが希薄な日本では宗教に世俗と離れた純潔さを求めがちなので、アル・グリーンの写真等から伺える根っからの芸人といった風情には違和感というか矛盾を感じたりします。1978年の「東京音楽祭」のグランプリを Belle (「愛しのベル」)で受賞した時の中野サンプラザでのライブ、"Tokyo ... Live" でも本人の宗教的な高揚感も伴った様子が聞けます(この音楽祭にはケイト・ブッシュやブロンディも参加していたそうです)。
"The Immortal Soul of Al Green"という4枚組のハイ時代の編集盤を聴くとまずハイ・サウンドを確立する前の音源に興味をそそられます。オーティス・レディング風に歌ったビートルズのカバー I Want to Hold Your Hand やジェイムス・ブラウン風の Get Back, Baby などは柔らかいシーツのようにセクシーな歌声とは違った一面が聴けたりします。全盛期の曲ではビージーズの How Can You Mend a Broken Heart は超絶モノのバラードで、彼の遠い親戚だったブルース歌手のリトル・ジュニア・パーカーに捧げた Take Me to a River のブルージーなかっこよさなどなどたまらないものがあります。ハイはスタックスと同じメンフィスのレコード会社で、スタックスがブッカー・T&ジ・MGズ解散前後に割とポップになったのに対して、ハイはストリングスを使ったり叙情的なギターが入るようになったものの以前のスタックスの音を継承した感じです。というのもMGズのアル・ジャクソン・ジュニアがハイでの録音によく参加して、メンフィス・サウンドの極意「ノリと簡潔」をハイ・リズム・セクション(主要メンバーは、ハワード・グライムズ(ドラム)、ティーニー・ホッジズ(ギター)、リロイ・ホッジズ(ベース)、チャールズ・ホッジズ(キーボード))に伝授したということがあったからです。そういう滑らかな絹のような音に乗ってアル・グリーンは愛の歌を囁き、時には神を意識した言葉を口にします。全盛期の彼の歌声は俗世間と信仰の狭間で揺れ動いていたからこそ、現在の牧師兼歌手といった落ち着きとは違ったその時にしかない輝きがあったのかも知れません。
上のようなことを書いた後にも、アル・グリーンは新作を出しています。"I Can't Stop" と同じくウィリー・ミッチェルと組んだ "Everything's OK" では、アル・グリーン「牧師」と書いてはいるものの歌声にエンジンがかかってきたようで、You Are So Beautiful のカバーなども実にしっくりきます。Another Day などでのアルのアドリブでの説教師のような力強い声は、二人にとってアルがゴスペルに向かった以降の物語の続きを聞いているような感じです。(こう書いた後、ウィリー・ミッチェルは亡くなってしまいました。ご冥福をお祈りします。)そして最新作の "Lay It Down"では、ジェイムス・ポイザーとアミール・"クエストラヴ"・トンプソンというネオ・ソウルのプロデューサーがウィリー・ミッチェルの代わりに入っています。これはアル・グリーンの曲でも特に浮遊するようなメロディがかっこよかった、端的に言えば Love and Happiness の世界を再現するという手法で、まさにヒップ・ホップ世代の「昔の一番いいところ取り」の良い面が現れているなかなかの作品です。ゴスペルの力強さよりもファルセットの柔らかさが前に出ていて、その声にコリーヌ・ベイリー・レイのような可憐ながらも芯の通った声が絡んだ Take Your Time なんかはもうたまりませんね。アンソニー・ハミルトンとかジョン・レジェンドといった今の時代でも歌心のある若手と組んで、今の音楽から遠ざかっている人にとっても納得がいく作りです。ジャケットに写るアル・グリーンは本当に昔とあまり変わらず、その変わらなさ加減がちょっと怖い気もしますが。(2005.08.28)(2009.02.05)(2010.01.17)