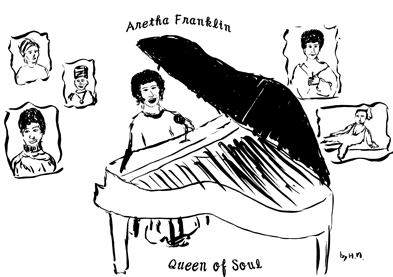
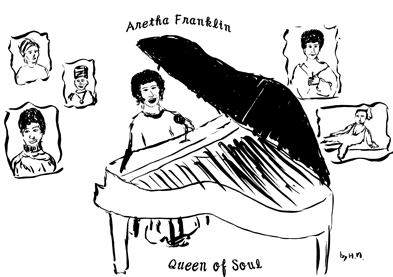
アレサ・フランクリンの曲をはじめて体験したとなると、私の場合は80年代のアリスタ時代の曲ということになります。Jump to It や Freeway of Love やジョージ・マイケルとのデュエットの I Knew You Were Waiting (「愛のおとずれ」)などは当時の私には取っ付きやすかったことは確かです。アリスタ時代の"Greatest Hits (1980-1994)" は、人工的なリズムに免疫がある人なら彼女のダイナミックな歌い方共々楽しめるものなのでしょう。ところがそういうアリスタでの曲も、彼女のアトランティック時代の曲の魅力にはとても勝てるものではありません。図書館に置いてあった "30 Greatest Hits"や日本盤の 「貴方だけを愛して」や 「レディ・ソウル」を聴いた日にはすっかり降参状態で、借りるだけでは飽き足らずに買った日にはそりゃもう何度遊んでも飽きることのないおもちゃが手に入ったような気分でした。アップ・テンポの曲もノリにあわせるだけでなくメロディの上を跳ねるようで、バラードはまろやかなメゾソプラノの声質にうっとりさせられます。多くの歌手の高音がナイフの切っ先のような鋭さを感じさせるのとは一線を画する、まだその先があるような余裕を感じさせる声です。その声にアトランティックのスタジオでマッスル・ショールズの人が中心になって奏でる音や、マイアミのクライテリア・スタジオで繰り出される音と結びつくのは、まったくこの上ない絶妙な組み合わせです。南部のミュージシャンを起用した音が当時の流行であっただろうし、曲の構成が特に工夫をこらしたわけではないのですが、とにかく何が起こるか分からなくてしかもいつも新鮮で面白い音というのは、特に80年代のアリスタ時代の安心感・安定感から求めるのは酷というものでしょう。
つい最近アトランティック時代の70年代後半まで網羅した4枚組の"Queen of Soul"を入手して聞き込んでいるのですが、特にしっくり来るのは先に挙げた二枚のアルバムの曲です。I Never Loved a Man (The Way I Love You) (「貴方だけを愛して」)の一切の無駄も妥協もない濃密さと、Do Right Woman, Do Right Man (「恋のおしえ」)のぜい肉を削ぎ落とした率直さは、彼女のアトランティック時代のはじまりとしては十分すぎるくらい幸先の良いものでした。Respect の突き抜け方、Dr. Feelgood のブルース、Chain of Fools のドライブ感、Since You've Been Gone (「愛する貴方を失くして」)のはじけ方、(You Make Me Feel Like) A Natural Woman の切実さなどなど、初期体験としては強烈すぎるものがあります。 バックのミュージシャンにスウィート・インスピレーションズのしっかりしたコーラスもそうですが、よくコーラスに加わったアレサの姉のアーマと妹のキャロラインの存在も見逃せません。アーマやキャロラインも凄い声をしているのですが、ピアノを弾かせても素晴らしいアレサの声には更に何か特別な「響き」があるとしか言い様がありません。彼女がオリジナルの Think や The House That Jack Built (実はセルマ・ジョーンズがオリジナルだったようです。"Respect : Aretha's Influences and Inspiration" で聞けます)や Call Me にノリのファンキーさがたまらない Rock Steady は勿論、ディオンヌ・ワーウィックの I Say a Little Prayer (「小さな願い」)やベン・E・キングの Spanish Harlem と Don't Play That Song のカバーもアレサ自身のものであるかのような輝きがあります。
アレサのような抜群にうまい歌手のライブ盤は安心して聞いていられる素晴らしいものが多いです。フラワー・ムーブメントのロック系のアーティストがよく出演した場所での「アレサ・ライヴ・アット・フィルモア・ウェスト」は、即席の組み合わせながらもキング・カーティスとキングピンズを始めとした凄腕のミュージシャンを従えたライブです。彼等が前座として聴衆を温めた様子もキング・カーティス名義でアルバムになり、その「ライヴ・アット・フィルモア・ウェスト」もとてつもなくかっこいい内容です。Love the One You're with (「愛への賛歌」)や Bridge Over Troubled Water (「明日に架ける橋」)や Eleanor Rigby といったどこかで聞いたことのある曲もアレサ達の手にかかればこの上なくファンキーに舞い上がる感じになります。そして彼女自身の Spirit in the Dark のゴスペル風味に続けて、客席のレイ・チャールズを上げて共演する下町ブルース風味の Spirit in the Dark で繰り広げられるリズムの変化は本当にたまりません。フィルモア・ウェストで腕を披露したギターのコーネル・デュプリーやドラムのバーナード・パーディーやコンガのパンチョ・モラレスが再び参加したロサンゼルスの教会でのライブ "Amazing Grace" は、ゴスペルのエキスが存分に味わえるこれまた凄いものです。その後出た "Amazing Grace : The Complete Recordings" のライナーノーツによると、当時出された曲には多重録音や聴衆が帰った後に取り直したものがあるそうですが、それでもこの濃厚さは少しも薄まっていません。父親のC・L・フランクリンが売れっ子説教師だったこともあり、幼少時からマヘリア・ジャクソンといった一流のゴスペル歌手と触れる機会に恵まれていたアレサは、ゴスペルにしては派手なギグをこなしたクララ・ウォードがある葬式で歌う姿を見て歌手になる決心をしたのだそうです。ピアノと男前の歌声を聞かせるジェームス・クリーヴランド牧師とサザン・カリフォルニア・コミュニティ・クワイアの手を借りて、世俗歌手のアレサがルーツのゴスペルに舞い降りて歌うのを聞くと、たとえそれが束の間の出来事だとしてもすべては許されるような感じにさせられます。1972年の音楽業界関係者だけに披露された "Oh Me Oh My" は当時未発表だったのですが、彼女のヒット曲が目白押しでバックの音の勢いも相まって圧巻のライブです。87年の "One Lord, One Faith, One Baptism" は "Amazing Grace" よりも教会の厳かさが色濃く出ているものの、フランクリン姉妹やジョー・ライゴン(マイティ・クラウズ・オブ・ジョイ)、そしてメイヴィス・ステイブルスとの素晴らしい競演が聞けます。
父親と共にツアーをしていたアレサは子供の時代にもゴスペル録音を残しています。"You Grow Closer" というピーコックの音源では、ピアノだけの伴奏でより生々しい彼女の声が聞けます。世俗歌手としてスタートしたのは大手のレコード会社であるコロンビアで、"The Queen in Waiting"ではその時代の録音が聞けます。ビリー・ホリデイを意識したジャズ、ダイナ・ワシントンを意識したブルースにはやりのR&Bなど、あてがわれた様々なスタイルの曲をアレサは素晴らしい解釈で歌い上げています。ライナーノーツによると売り上げ的には不遇だったコロンビア時代をアレサは「よき思い出」のように振り返っていますがそれも現在の成功があるからで、環境のよい大手のレーベルで期待していた成功を得られなかったのは親子共々当時は複雑な心境だったことでしょう。彼女が本来の素晴らしい自分の素質とは違うものを求めたがるのは、後のアトランティックでの70年代中期以降のアルバムのジャケットの写真からも伺えます(体重の増減が激しかった彼女は時々女性らしさを強調した姿も披露していますが、世間が彼女に求めているイメージはやはり母性でしょう)。とはいえ、ツボにはまった時の極上の味わいはそういうささいな迷いも吹き飛ばすものです。 (2005.12.11)(2009.06.21)