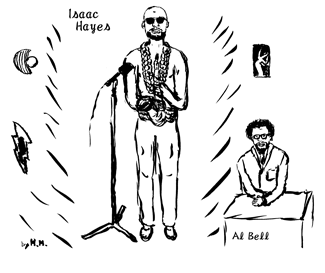
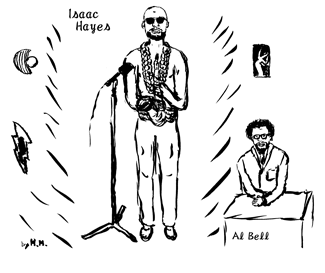
メンフィスのスタックスは1960年代に自前のミュージシャンと作曲陣でソウルの良作を作り続けたレコード会社です。自社の看板に「ソウルズビル・U.S.A.」と印してモータウンの「ヒッツビル・U.S.A.」と対比させていたのはまさに「名は体を表す」というものでした。ところが、オーティス・レディングが飛行機事故で亡くなった翌年の1968年にアトランティックとの配給契約が切れたのを境にスタックスの作り出す音楽に明らかな違いが現れはじめました。それまではオーナーのジム・スチュワート主導の趣味の色が濃く、バックバンドのブッカー・T&ジ・MG'sとメンフィス・ホーンズの割かしルーズな演奏がスタックスの音そのものでした。ところがやり手のアル・ベルが共同オーナーとして実権を握ると、ストリングスなどの音も加えたりして売れ線でポップな曲も作るようになり、マッスル・ショールズなどのほかのスタジオで録音したり、スタックスとは無縁で完成した曲を配給したりと、「メンフィス・サウンド」という特徴的なものが無くなってしまいました。それでもアーティスト自身の個性がそのまま曲に反映されるようになったとも言え、その中でもアイザック・へイズは独自な道を自ら切り開いた特異な存在といえます。
売れる前にも一応シングルやアルバムも出したことがありましたが、彼はデヴィッド・ポーターと共に主にサム&デイヴに名曲を数多く提供していた裏方でした。そんな中、配給契約が変わりアトランティック時代の権利を失った曲の分に見合うアルバムのカタログを作ろうという会社の方針により自分自身がレコードを出すというチャンスを得ました。その時の粗製濫造されたアルバムが殆どヒットしなかった中で、"Hot Buttered Soul"というアルバムは商業的に成功してスタックスを窮地から救っただけでなく、その内容もその後の黒人アーティストのあり方に大きな影響を与える画期的なものでした。R&Bやソウルのアルバムはヒット曲とカバー曲を寄せ集めたもので、2、3分の曲が二曲入ったシングルの売り上げで商売するという考えが一般的でした。しかしアイザック・へイズのアルバムは5分から20分近くの曲を四曲おさめたもので、バックバンドのバーケイズの生み出すスローなリズムに歪んだギターやストリングス、ホーンをからめて、ヘイズ自身の低いセクシーな声が畑違いのポップス(ディオンヌ・ワーウィックの Walk on By、グレン・キャンベルの By the Time I Get to Phoenix)をカバーして、時々イントロに長い語りを入れたりするスタイルでした。ちょうどFMラジオが黒人リスナーにもよく聞かれるようになった時期で、控えめなしゃべりのDJがそういう長いジャズっぽい曲を流すのかっこいいということだったのでしょう。1970年代にスティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイ、カーティス・メイフィールドが自分のプロデュースで長い曲も納めたコンセプト・アルバムを出すようになるのですが、アイザック・へイズはまさにその先駆けでした。そして黒人の監督で黒人が主役の映画のサウンドトラックの"Shaft"(「黒いジャガー」)でアカデミー賞をもらうなど、後の「ブラックスプロイテーション」の映画とサウンドトラックの先鞭をつけたことでも評価されています。
"Hot Buttered Soul"のスキンヘッドのアップというジャケットに私は釣られてつい買って聞きました。1曲1曲を集中して楽しむというより緩いノリと気分を味わうというもので、最初の印象は少し退屈なものでした。それでも Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic の歪んだギターがギンギンのファンクはカッコよくなかなか侮れないものと感じました。その後 Theme from Shaft をラジオで聞いた時は是非CDで聞きたいという衝動にかられました。この曲は16ビートのハイハットの刻みから曲が始まり、ワウ・ギター、ベース、ホーン、ストリングスと音が重なる長いイントロの後、ヘイズが「おいらはシャフト。女にも腕っぷしも強いぜ」といった歌詞(?)をぼそぼそと歌い喋るというもので、曲の構成とアイデアは抜群で一回聞いただけで耳に残るものでした。アルバムの"Shaft"はこの曲以外はインストが多く、映画を見ながらでないとイマイチピンと来ないものでした。オリジナルアルバムの"Movement"や"... To Be Continued"も緩いノリと気分は健在でも、"Hot Buttered Soul"のアイデアの二番煎じ、三番煎じという感じにしか受け取れませんでした。今思えば、スティーヴィーやマーヴィンが安定したモータウンで自由な創作活動を許されたのに比べて、やたらと規模を拡大して自転車操業に追われたスタックスの屋台骨を支えていたアイザック・へイズは、最初こそ創作で主導権を握ったもののじっくり新しいものに取り組む余裕がなかったのかも知れません。経営者のアル・ベルが政治活動にものめり込みアイザック・へイズもその片棒を担いでいた一方で本人の曲自体はメッセージより娯楽に徹したもので、スティーヴィーやマーヴィンが曲でメッセージを全面に打ち出し世間的に高く評価されがちなのと比較するとなかなか興味深いものを感じます。二枚組の"Black Moses"ではカバーばかりでなく殆どラップのノリの自作曲 Good Love を取り上げたり、ジャクソン5の Never Can Say Goodbye のカバーなどでは意外と綺麗なファルセットで歌ったり、"Joy"、"Chocolate Chip"や"Groove-a-Thon"のそれぞれのタイトル曲ではディスコ寄りの軽快さが現われたりしますが、なかなかコッテリとした独自性の強いものです。つい最近出たライブ盤の"At Wattstax"での聞き物は、自身のサックスまで披露しているビル・ウィザースの Ain't No Sunshine とレイ・チャールズの Lonely Avenue のメドレーで、10万人以上の観客を前にスタックスのアーティストの大トリを務めるアイザック・ヘイズにしてみれば、天にも昇るような感覚だったことでしょう。
全体を通して言えるのは、アイザック・へイズの才能は新しい楽器やテクノロジーやリズムをまっ先に取り入れるというより、既に巷にある音を独自に組み合わせて自分の世界観を作り上げるという点にあるのだと思うのです。この感覚は後のラップやヒップホップにも通じるものです。スタックスが破産して大手のポリド−ルに移った後は創作に力を入れるというよりディスコとか流行に身をゆだねるという趣きで、"The Best of The Polydor Years" も低いセクシーな声は健在です。思わずシックの「おしゃれフリーク」を思い出すような Zeke the Freak のような曲もありますが、ロイ・ハミルトンの59年のロカビリー風の曲のカバーである Don't Let Go は、音の分離の良いスピーカーで聞くと女性コーラスが茶々を入れる間をヘイズの低い声が下の方から蛇のようにニュルーと出てくるようで、違いの分かる大人の音楽という感じで「やってくれるな」と思わせます。そういう下世話な娯楽に徹したアイザック・へイズは、多少自信家であっても「わかってる奴だぜ」という感じで結構好きだったりします。(2004.09.13)(2006.01.08)