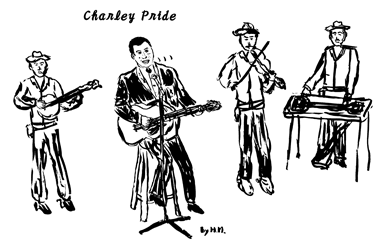
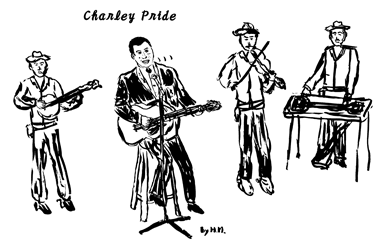
明治時代以降の西洋音楽の基礎がある作曲家と西洋音楽に日本語を乗せるのに苦心する作詞家が職人として曲を歌手に提供し、歌手が「こぶし」を始めとする独特の歌唱法を守って披露する。演歌が生まれた当初は新鮮でそれがそのまま流行歌となったものの、時が経つにつれてその型とそれを取り巻く仕組みが膠着して古臭くなり、それでも飯を食っていくためにその閉じた世界にこだわり続ける。思えばクラシックもジャズもそういう道をたどって行ったし、アメリカのカントリーもそんな印象です。それでもカントリーはカントリーなりに活性化させようという動きがあったりします。ギター、バンジョー、フィドルなどの弦楽器主体の音楽であることもありロックやポップスとの交流が割とあるし、最近はマッチョなナイスガイといった兄ちゃんとか結構きれいでタフな姉ちゃんとかがルックスもウリにしていたりと、日本の演歌とは比べ物にならない程元気です。今回取り上げるチャーリー・プライドはどちらかといえばカントリーの「閉じた世界」の象徴みたいな人ですが、かなり独特な立場にあった人です。
私が音楽に興味を持ち始めた頃はテレビもラジオもヒットチャート番組が全盛で、歌謡曲のはやり廃りに振り回される感じでした。そのなかに演歌が何曲か紛れ込んでいて、客を入れたテレビ番組等でその違和感はいっそう浮き彫りになりました。アイドルの出演でけたたましい歓声があがるのに、演歌歌手が登場したとたん冷ややかな空気が流れ込んだかのような反応を客は見せたものです。そういう演歌でもメロディとかが記憶に残っていて、そういう子供の頃の音楽体験は後の人生にも影響を与える、というのは私だけではないはずです。チャーリー・プライドは南部のミシシッピー州出身の黒人で、教会のゴスペルや街角のブルースに触れる機会はあったはずですが、彼が子供の頃の1940年代、50年代始めのラジオ局は専ら白人向けのもので、一番お気に入りだったのはカントリーを流すラジオだったのだそうです。When a Man Loves a Woman (「男が女を愛する時」)を出したサザン・ソウルの歌手、パーシー・スレッジもカントリー局を聴いて育ったそうですが、パーシー・スレッジがドゥー・ワップのグループを組んだりしてソウルの道に進んだのに対して、チャーリー・プライドがそうならなかったのは声の質がカントリーに向いた深いバリトンだったこともありますが、最初から彼が歌手を目指していたわけではなかったことも原因かも知れません。若い頃の彼はニグロ・リーグの有望な野球選手でメジャー・リーグを目指していたそうで、怪我とかで挫折した後は家族を養うために北西部のモンタナ州で亜鉛の精練工をしつつ歌手としてナッシュヴィルを目指すようになりました。
60年代の黒人の社会進出には公民権運動とそれに伴う人種間の摩擦がつきもので、チャーリー・プライドも「黒人初の成功したカントリー歌手」という立場からしたらその文脈で語られてしまいそうです。ところが彼のベストのライナーノーツによると、彼はただ単にカントリーを愛していてその歌声で白人が殆どのカントリー・ファンを納得させていったという話が中心になっています。確かに全盛期だった彼の60年代後半から70年代前半の曲は弦楽器主体の伝統的なカントリーで、奇をてらった編曲や歌詞は一切ありません。それに彼が公民権運動に積極的に関わっていたとしたら、カントリー界は過剰に警戒して彼を受け入れることはなかったでしょう。そうは言っても「はじめて」というのは何かと壁があったりします。彼のデビュー時の逸話によると、舞台の上でも広告にも本人が姿を現さないとか、特に黒人の男性が白人の女性を誘うことを連想させる歌詞を題材にしない(デビュー曲の Snakes Crawl at Night は間男を引込んだ妻を殺めた哀れな男の話でした)とか、そういう変な配慮はありました。それでも大手RCAの重鎮で偉大なギタリストでもあるチェット・アトキンスを始めとした人達が彼を応援する気になったのは、彼の声が何の捻りも加えていない上質なカントリー歌手のものであったからでしょう。
チャーリー・プライドが子供の時にはカントリーを聴いて歌った黒人は結構いたそうですが、今では様々なラジオ局が様々な曲をかけるし、黒人社会でわざわざ周囲の好みと異なるカントリーで身を立てようなんて思い付く黒人は殆どいないだろうし、音楽業界にしても売る戦略を立てにくい黒人のカントリー歌手に目をかける余裕はなくなっていることでしょう。チャーリー・プライド以降に成功した黒人のカントリー歌手は皆無に近いというのは、彼の存在が単発的だったのを物語っています。「受け入れられるべきものは受け入れよう」という60年代後半の寛容な雰囲気が重なって生じた彼のような存在は、今後ますます出ることはないでしょう。
チャーリー・プライドの"RCA Country Legends"や"The Essential Charley Pride"といったベストで聴ける曲は弦楽器主体の正統派のカントリーで、彼の安定したバリトン共々聴いててひたすら安らぐような安心感があります。ライブ録音のハンク・ウィリアムスの Kaw-Liga のカバーは、本家の情感の深くハラハラするような緊張感があるのと異なり、くつろいだノビのある歌声で観客を魅了するし、彼自身のヒット曲である All I Have to Offer You (Is Me)、Does My Ring Hurt Your Finger、I'd Rather Love You などはカントリー独特の物語のある歌詞を丁寧に歌うし、Is Anybody Goin' to San Antone、Wonder Could I Live There Anymore、Kiss an Angel Good Mornin' などは結構ポップで陽気な感じです。Mississippi Cotton-Delta Town は彼の貧しい子供時代を反映しつつも淡々と良き昔を振り返るような内容で、レイ・チャールズもかつて取り上げた Busted はフィドルのズシリとした演奏がこの曲がカントリーであることを思い出させます。「閉じた世界」で求められる音楽は新鮮で刺激的なものではなく昔と変わらず安心できるものです。音楽になにか意味を求める以前に「聴いていて気分がいい」という心地よさを求めるなら、チャーリー・プライドの音楽にはそれがあります。ロックとかソウルとか未だにこだわる自分にはかったるい場面も時々ありますが。(2005.07.10)(2007.08.04)