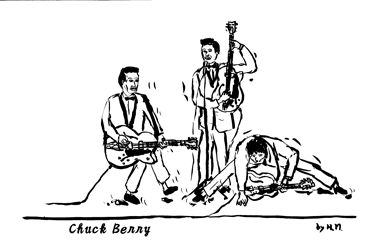
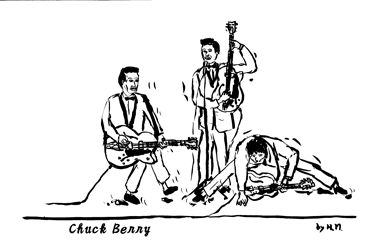
ドラムやピアノやサックスなどロックンロールする楽器はいろいろ有りますが、中でもヴォーカルと同じくらい目立つのはやはりギターでしょう。ロックンロールは戦前のブルースやビッグ・バンドの流れを汲むリズム&ブルースに加えて、ヒルビリー等のカントリーに由来するロカビリー、ゴスペルからのドゥー・ワップをも含めたとにかく賑やかな音楽です。その中でどの楽器を中心に置くかによって曲の内容だけでなく演じる人の背景までも色分けされるようなところがあって、ギターはとりわけ「白人が演じるあまり踊れないロックンロール」の楽器という印象です。チャック・ベリーのギターはブルースの雰囲気もありますが特に弦楽器主体のカントリーの速弾きの影響が大きいようで、Johnny B. Goode の高速のシャッフルに8ビートが入り交じったリズムでは男女が何かを期待して踊る時の間みたいなものがあまりありません。チャック・ベリー自身は黒人としての矜持があったことは彼の一部の歌詞から伺えますが、彼の音楽が10代の白人に受け入れられやすく真似されやすかったのは、色気の少なくて直情的にギターをかき鳴らすというスタイルのおかげなのかも知れません。
自分の持っているCDのライナーノーツにはチャック・ベリーのちょっとした伝記が載っていて、彼のギターに影響を与えた人達の名前が出てきます。学生時代の友人、テナー・ギターの教則本、近所の床屋、ルイ・ジョーダンのジャズのスウィング、T・ボーン・ウォーカーやマディ・ウォーターズのブルースが、彼がプロになる前の先生です。セントルイスでジョニー・ジョンソン・トリオをバックにプロとしてそこそこ稼げるようになった頃の演目は、ジャズ・スタンダードのナット・キング・コールからマディ・ウォーターズ、カントリーのハンク・ウィリアムズまでに及んだそうです。シカゴに移った彼はマディ・ウォーターズの紹介でチェスに入ることになりますが、彼のデビュー曲 Maybellene はカントリーの曲 Ida Red を少し下敷きにしたものでありました。チェスはシカゴ・ブルースの総本山であったことから、「チャックはブルースを忘れていない、いや、忘れるものか」という視点で編集された "On the Blues Side" では、初期の自作曲の Wee Wee Hours 、No Money Down や昔のジャンプ・ブルースの Confessin' the Blues などで確かにチャックのブルースが聞けます。とはいえ、彼のギターはやはり彼自身が元祖といってよい演奏スタイルです。エレキギターがアンプを通して歪んで荒々しい音を出し、ドラムとベースがリズムを刻む。そういう曲がDJのアラン・フリードのような人達の仕掛けによってロックンロールという名前を得たわけです。
チャック・ベリーはギターもそうですが詩人としても素晴らしいものがあります。Brown Eyed Handsome Man は黒人である自分のプライドを忍ばせつつさらりとした洒落っ気を発揮している歌で、彼の歌では一番最高だと私個人は思います。Reelin' & Rockin' は繰り返しのメロディが歌詞の韻の組み方のおかげで単調でなくその続きを聴きたくなる侮れない魅力があります。それだけでなく Maybellene や You Can't Catch Me のスピード感のある車にまつわる話。Thirty Days、Too Much Monkey Business や Roll Over Beethoven にビーチ・ボーイズの Surfin' U.S.A. の元歌である Sweet Little Sixteen の言葉の引き出し具合。School Day やOh Baby Doll の10代の白人の聴衆を意識しつつ当事者から一歩離れた観察眼。Downbound Train や Memphis, Tenessee の哀感などなど。"His Best, Volume 1"や二枚組の"The Anthology"の一枚目で聴ける1957、8年までのチャック・ベリーの曲はロックンロールの基礎と言っていい程の輝きがあります。
59年以降は自身の経営するクラブで未成年者を働かせていたこと等に関する罪で裁判沙汰になり62年から64年まで塀の中に入る羽目になったこともありますが、アメリカ社会の保守的な圧力のせいかロックンロールが大人しくなり、チャック・ベリー自身も発想が行き詰まった感が否めません。出所後はビートルズ、ローリング・ストーンズ、ビーチ・ボーイズを始めとした「弟子」を通して再評価され、気分的に吹っ切れたなかなかの曲を出しています。"His Best, Volume 2"や"The Anthology"の二枚目に収録されている Nadine、No Particular Place to Goや Promised Land なんかは、もうロックンロール全盛時に10代だった人たちが成熟したこともあって、結構いい歳になったチャック・ベリー自身が自分の地をそのまま出しているような感じです。70年代のロンドンでのライブの My Ding-A-Ling (元歌は50年代始めのニュー・オーリンズの大御所デイヴ・バーソロミューで"The Very Best of King/ Federal/ Deluxe Vol. 1"で聴けます)と Reelin' & Rockin'では、ロック・スターと聴衆との互いに心得た会話みたいなものが繰り広げられています。
他にもエルヴィス・プレスリーに負けず語れることは山ほどありますがここではその余裕がありません。まとめといってはなんですが、ロックンロールが白人のお気に入りになる一方黒人にとっては次第に馴染めないものになっていったのは、ロックンロールがテレビ等を通じてスターを作り上げて聴衆との上下関係がある意味で出来上がり、聴衆同士が一緒に踊れる音楽ではなくなったことにあるのかも知れません。黒人の成功者であるが故に紆余曲折ある人生を送ったチャック・ベリーの「弟子」に黒人が殆どいないというのはなんとも皮肉な感じがします。とはいえ、今聴いても色褪せない彼のギターのスタイルはついつい自分もやってみたくなるような楽し気な魅力があるようです。(2005.07.03)(2007.07.28)