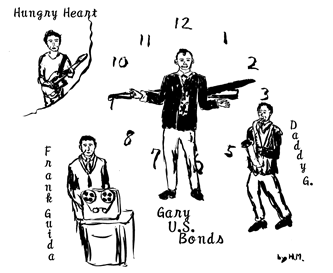
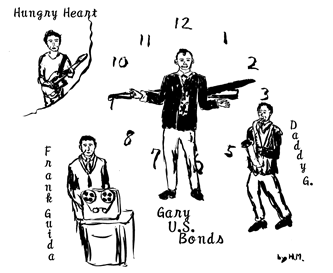
それにしても「アメリカン・バンドスタンド」というアメリカのテレビ番組はバッタもんの宝庫です。1957年にディック・クラーク司会で全国ネットで平日の夕方に放送されるようになったこの番組では、当初はまだ人種差別が表立っても許容された時代ということもあってR&Bのヒット曲を黒人が自らそのままやるよりも白人がカバーして歌ったりすることが多かったのです。それでも例えば What'd I Say (「ホワッド・アイ・セイ」) をエルビス・プレスリーが取り上げたことでレイ・チャールズが白人に認知されるきっかけになったように(こう書いたのはレイのインタビューでの発言から)、そういうカバーが将来の「クロスオーバー(黒人の曲が白人にも売れること)」につながることになります。とはいうもののそのカバー自体は殆どが音楽センス的にはかなり疑わしいものがありました。感傷的なポップスで有名な白人の歌手が歌ったR&Bのカバーはなかったことにされているような状態です。その一方でチャビー・チェッカーやロイド・プライスのように白人に受けるような形でテレビ番組に進出し始めた人達も出てきて、ゲイリー・U.S.・ボンズもその中の一人でした。テレビの歌番組では口パクが殆どとはいえ、アップテンポのロックンロールをハスキーな声でシャウトする他のヤワな白人よりもはるかに迫力ある彼の姿を見て影響された人は多く、ブルース・スプリングステイーンなんかはE・ストリート・バンドと共に彼の1980年代初期の復帰作に手を貸したりしたりした程です。
米軍放送のFEN(今のAFN)のラジオでウルフマン・ジャックといったDJがご機嫌なロックンロールをよく流していて、ゲイリー・U.S.・ボンズ等もかけていたように記憶しています。その後今さらながらレグランド・レコードでの全盛期の録音が収録されているベスト盤の"The Very Best of Gary U.S. Bonds"やレア盤の "Take Me Back to New Orleans"を買って聴いたりするわけです。ヴァージニア州のノーフォークのレーベルのオーナーでプロデューサーのフランク・ガイダがボーカルやコーラスやホーンを重ね録りして出来たのは、音抜けが悪いそれでも妙な迫力がある音です。少しでもノイズとかが入れば大騒ぎになる「品質管理」の行き届いた現在とはえらい違いです。New Orleans の「ヘーイ・ヘイ・ヘイ・ヘーイ・イェー」は日本でもロックンロールの代名詞で、Quarter to Three や School Is Out は「パパやママは置いといて自分らで楽しむ」というロックンロールの典型的な題材の歌詞で、例えばフィンガー5の「学園天国」を思い出させます。曲の途中によく出てくるダディ・Gことジーン・バージのサックス(New Orleans ではアール・スワンソン)を始めとするチャーチ・ストリート・ファイヴの演奏は荒々しさに満ちています。Dear Lady Twist や Twist, Twist Senora は徴兵時にトリニダードに行っていたというオーナーの趣味も混じったカリプソ風味です。I Wanta Holler (But The Town's Too Small) はお蔵入りだったもののジャングルを思わせるビートとファンキーなオルガンがなかなかの曲です。自分自身のヒット曲の二番煎じ、三番煎じが多いのは1960年代前半まではどこでもやっているから愛敬みたいなものです。「おれたちのアイデアをパクリやがって」なんていう Copy Cat のような大人気ない内容の曲もありますが、モコモコとした何かが詰まったビッグ・ビートに乗ったシャウトはやはり独特の味があります。
21世紀になって60歳を過ぎてもライブ盤の"King Biscuit Flower Hour Presents"で聞けるように元気だし、Out of Work や This Little Girl of Mine なんかはブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」などを思わせニヤっとさせられます。彼が復活した80年代初期のヒット曲を収録した"The Best of Gary U.S. Bonds(EMI)"はE・ストリート・バンドによるロックンロールで、聴いていて気持ちいいのですがレグランド時代のドサクサに紛れる感じがありません。R&Bやソウルではレーベルごとにバック・ミュージシャンがその独自な音を築きレーベルどうし互いに意識しあいながらいくつかの流れを作っていくのですが、ゲイリー・U.S.・ボンズのレグランドのように一つのアイデアの元に流れから孤立したような音が出たりします。CDのライナー・ノーツによるとレグランドの音を過度に変調させても迫力を出すというやり方はあちこちで真似されているなんて主張されていますが、この音ぬけの悪い曲づくりはさすがに真似されずその意味では孤立した音だと私は思います。後が続かずに時代の徒花となりがちなものの中にも何か心に残るものもあるということです。(2004.08.15)(2005.09.05)